新刊の紹介~日本研究書籍「日本の宗教」出版
6月2日、ソフィア市第18総合学校副校長兼日本ブルガリア教育文化センター長、ブラティスラフ・イヴァノフ氏による日本研究書籍「日本の宗教」の出版発表会が、ソフィア市第18総合学校図書館で開催され、小泉大使からの祝辞が紹介されました。なお大使館より杉浦参事官が来賓として出席しました。
イヴァノフ氏は、これまで長きにわたり、日本語教育及び日本文学の普及に貢献されており、その功績を称えて日本国政府は平成21年春の外国人叙勲として同氏に勲章(旭日小綬章)を授与しています。
今回出版された同書を通じて、より多くのブルガリアの皆様に我が国への理解を深めていただければ幸いです。
また、同書発刊につき、著者のイヴァノフ氏より、以下の通り紹介文を頂きましたので、掲載致します。
本書は、ブルガリア人が書いた初めての日本の宗教に関する総合図書といえるでしょう。日本の宗教の歴史は、大きく分けて古代から538年の仏教公伝までと、538年から現代までと2つの時代にわけられます。
最初の日本宗教は、「神道」と呼ばれるもので、紀元前からの日本人の信条や祭儀慣習のもと、広まるようになりました。約4世紀から大陸文化(仏教や儒教など)が神道に大きな影響を与えるようになりましたが、それでもその独自性や、ポリティズムやアニュミズムといった基本的特質、聖なる物の不可視性、聖なる教えの口頭伝授の伝統などを保っていました。
日本宗教の本質というと、神道、仏教、儒教が一体となっているようなイメージがありますが、それはすべてがごちゃまぜになったものという意味ではなく、むしろ神道をベースにして仏教と儒教という糸が織り込まれた布のようであると思います。この布を構成する糸はその一本一本をたどることができるものの、布全体が日本の宗教といえます。一つに焦点を定めようという取り組みは、全体を破壊することにつながると思います。これは、日本人が自身の宗教属性に関する質問に対して答えられないことの一つの理由と言えるでしょう。日本人は人生の要所要所で、仏教や神道と関わりがある一方、儒教的倫理は、日本社会において基本的行動規範の役割を持っています。儒教概念のいくつかは、原始的な神道の概念と交わり、倫理的責務となっており、現代の集団倫理は儒教理念に基づいているといえます。
日本の比較宗教学の創設者加藤玄智によれば、日本人は生まれながらに仏教徒でありながら神道徒でもあります。この概念のもと、本書の主題は、日本人の歴史においては神道は精神的支柱であり、そのおかげであらゆる宗教的伝統から民俗文化の総体が形成されているということであります。神道をもとにクロノトープー時間や空間に関する伝説的・信仰的概念であり、真実、良識、美の基本的価値体系を与えるものーの伝統的モデルが形成され、仏教によって日本文化にカルマ-存在から存在へと移り変わる考え、行動、行為の結果―という概念が持ち込まれました。カルマは過去の罪の現れであり、その意味で人は自身の運命だけではなく、次の世代の運命をも背負わなければならないことになります。
神道、仏教及び儒教間の融合への何世紀にもわたる挑戦の結果生み出された宗教的混同主義は、全体として精神世界そのものの融合をも運命づけています。我々が宗教と侍倫理の形成のつながりに目を向けるならば、また神道、仏教、儒教をわけて考えることができないことを思い知らされるでしょう。優れた倫理観と義理や名誉といった概念は儒教から、死への侮蔑は仏教から、自制の精神は禅から、限りない愛国主義は神道から生まれています。
 |
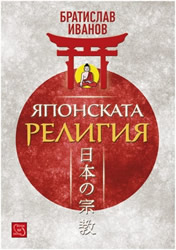 |
出版発表会の様子 |
「日本の宗教」の表紙 |
